クマ対策カメラで命を守る!クマ被害を防ぐ「見える化と自動威嚇」──新しいクマ対策のかたち

ここ数年、北海道だけでなく東北や本州各地で、ヒグマやツキノワグマによる人的被害や出没が相次いでいます。2025年度も10月末時点で196人が被害に遭い、そのうち12人が命を落とすなど、クマ被害は「どこに住んでいても他人事ではない」状況です。
こうした状況を受けて、現場ではさまざまな対策が講じられていますが、中でも注目されているのが「カメラの力を活用した被害防止策」です。とりわけ、人目が届きにくい場所や電源の確保が難しい山間部などでは、電源不要で即時設置が可能な監視カメラが“人の目の代わり”として期待されています。
目次
なぜカメラが有効なのか?

クマの出没は、ほとんどが早朝・深夜など人の活動が少ない時間帯に起きます。また、視界の悪い山道や林道では、突然の遭遇を避けることが難しいという問題があります。こうした条件下で、常にその場に人を配置するのは非現実的です。
そこで、カメラによって出没を「見える化」し、リアルタイムで人に伝えるという仕組みが、被害を未然に防ぐ有効な手段として注目されているのです。
クマ対策に求められるカメラの条件
効果的なカメラ運用のためには、単に映像を記録するだけでなく、次のような機能が必要です。
動物検知・自動通知
人感センサーやAIを搭載し、動きを検知した際に即座にスマートフォンなどに通知。大型動物と人間を識別できるシステムなら、誤報を減らしつつ素早く対応が可能です。
夜間対応
人里に下りてくるクマは、人との遭遇を避けるため、夜間や早朝・夕方の薄明薄暮に活動する傾向があります。そのため、赤外線暗視機能や低照度でも撮影できるカメラが効果的です。暗闇でも鮮明に動きを捉えることが、人命を守る鍵となります。
威嚇機能(音・光)
検知時には警報音やLEDライトによる強い光を発し、音と光の両方でクマを威嚇して追い払う効果が期待できます。特に母グマは子グマを守るために神経質ですが、人の存在を察知すると多くの場合は自ら退避します。そのため、こうした仕組みを導入することで、不意の遭遇を未然に防げる可能性が高まります。
配線不要・電源不要
山間部や電源の通っていない林道・農地などでは、ソーラー充電や内蔵バッテリーで稼働するカメラが理想的。設置も簡単で、専門知識がなくても即日運用を開始できます。
現場で進む導入と成果

例えば、北海道・知床では、環境省が観光地での過度なヒグマ接近を防ぐ目的で監視カメラを導入。観光客の滞在状況やヒグマの行動を可視化し、ルール遵守を促しています。
富山市では、AI搭載カメラと防災無線を連携させ、クマ出没を自動で住民に伝えるシステムを試験運用。これにより、被害の早期予防と迅速な回避行動が実現されています。
また、国営の自然公園などでは、センサーカメラとクラウド連携を組み合わせ、職員が遠隔で確認できる仕組みも導入されており、出没後のエリア閉鎖や避難指示などに活用されています。
命を守る道具としての「簡易設置型カメラ」
最近では、電源工事不要・通信回線不要で、すぐに使える監視カメラ製品が登場しています。例えば、ソリッドカメラの「電源不要型センサーカメラ」は、ソーラーパネルと一体型の設計で、現場に置くだけで即時稼働が可能。通信機能も内蔵されているため、スマートフォンでの遠隔監視も可能です。
さらに、センサーが動物の接近を検知した際には、警報音やライトでクマを威嚇する仕組みも搭載されており、非常に実用的です。特に、通学路や人家の近くなど「人の生活圏にクマが出る」地域では、こうしたカメラの導入が被害の抑止につながります。

防災の常識を変える、新たな「見守り」
監視カメラは、もはや防犯だけのツールではありません。自然災害や野生動物による被害から「人の命を守る道具」として、その役割が拡大しています。
クマとの共存を模索する今、こうした機器の導入は、地域の安全性を高めるとともに、「クマと人の距離」を適切に保つための第一歩です。
登山口や農地の縁、市街地と山の境界線──人とクマが交わる危険地帯に、簡易設置型・電源不要のカメラを一つ置くだけで、命が救えるかもしれない。
地域の皆さんが安心して暮らし、子どもたちが安全に通学できる未来のために。カメラによる「見える防災」の導入を、今こそ真剣に考えてみてはいかがでしょうか。
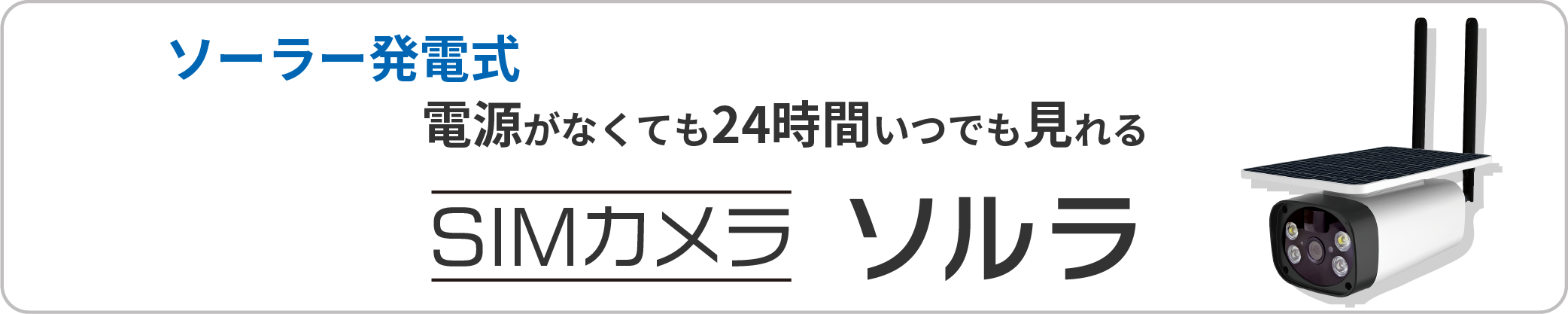
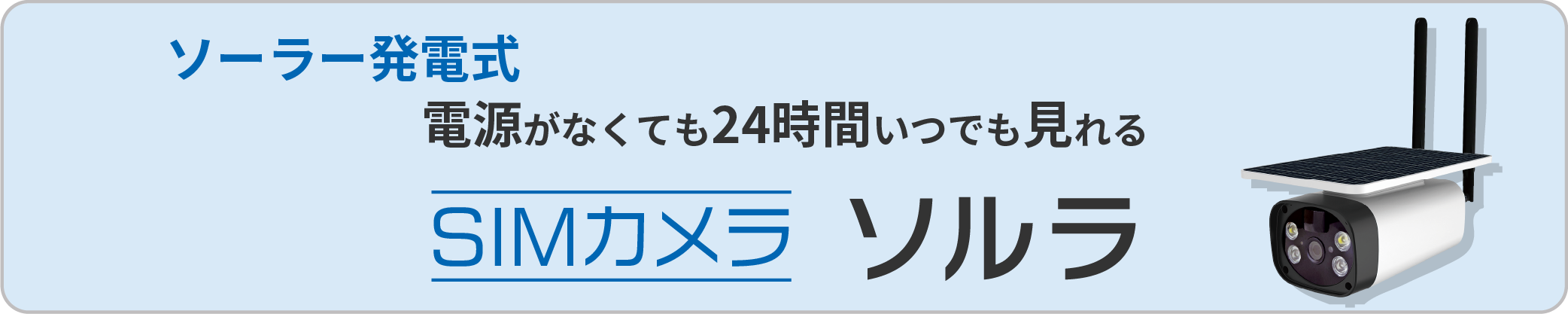


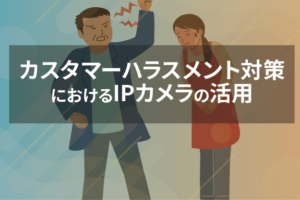
お客様の満足を
サポートします!